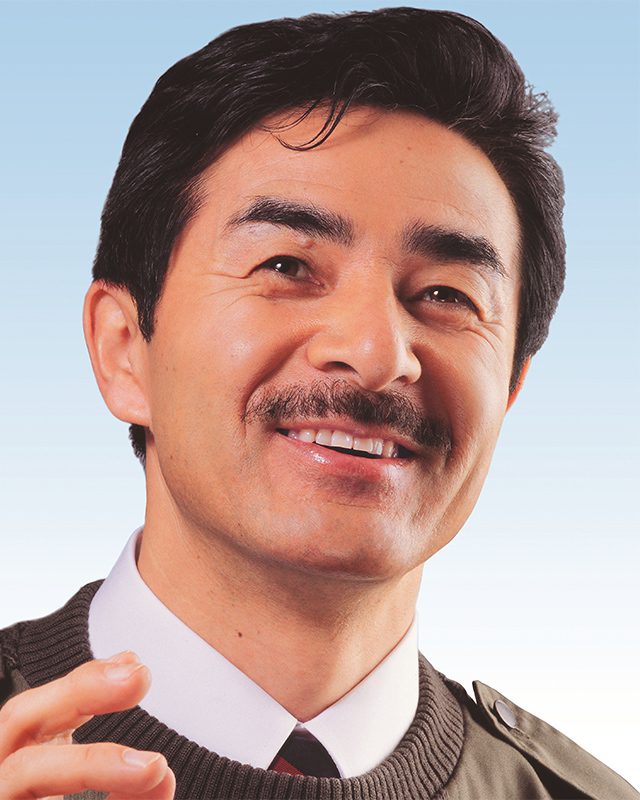先ほど私が給与法上どうも何か釈然としないと申し上げたのは今のようなことで、確かに教員は今は労基法は適用されていません。給特法なんですけれども、その分調整額が支払われていて、考え方としてはいずれは労基法に基づいた時間外勤務手当を支給する方向で今動いているという、その中にあって、当分の間調整額をどうするかという話になったときに、それをある条件に達しなければ支払わないとか、それが職場によっても違ってくるとか、こういうようなことを案の中に盛り込んでいるということ自体に私はどうも納得いかないものがありますと、これ、労働法制上おかしいのではないかというふうに指摘をしたのはその点です。
それからもう一つ、インセンティブの問題なんですけど、これは動機付けをして、それに対する報酬を与えるようなことがこのインセンティブの意味として考えられるわけですけれども、これは誰に一体そのインセンティブが働いているのかという問題なんですが、これは、教員は好きで残業をしているわけではなくて、増えるばかりの業務量を限られた人数でこなすしかないわけで、どんどんそれで仕事が増えていくわけですね。だから、業務量を減らしてほしいと。そのことについては財務省も実はおっしゃっていて、これは文科省もっと頑張れということを今回も指摘をされているんです。
それは私も全く同感で、これはその文科省や教育委員会が、教員がやらなくてもいい業務をもっと明確に指示をして、それをしたら罰則を与えるぐらいのことをやっていいんじゃないかと私は思っているんです。でも、それがなっていない。これは、例えば、業務量を減らすということの動機付けを教育委員会や文科省にはすべきですけれど、その手当を受ける、調整額を受けるのは教員ですから、それがインセンティブとどうつながるのかというのは、大臣何かうなずいておられますけれど、私自身そこがどうも納得いかないわけですね。だから、この案は非常に粗いというか、こなれた考えだなと思えてなりません。
加藤大臣は厚労大臣の御経験があり、働き方改革、処遇改善など精力的に取り組んでこられた方ですので、是非この点は誠意を持って文科省とは当たっていただきたいなというふうに思います。
ちょっと時間がありませんので次の質問に移りますが、産休、育休代替教員の正規化についてお伺いします。
これは、今回建議の中で出されているんですけど、私は非常に効果的な取組だと実は思っておりまして、以前、私自身もこれについては是非実施をしてほしいという、別の委員会でしたけれども、求めてきたことがございます。是非文科省としてこの正規化について取り組むべきだと考えます。そして同時に、法令上対応をしなければならない必要があるとすればどういうことで、いつから実施を考えているのか、お答えをいただきたいと思います。