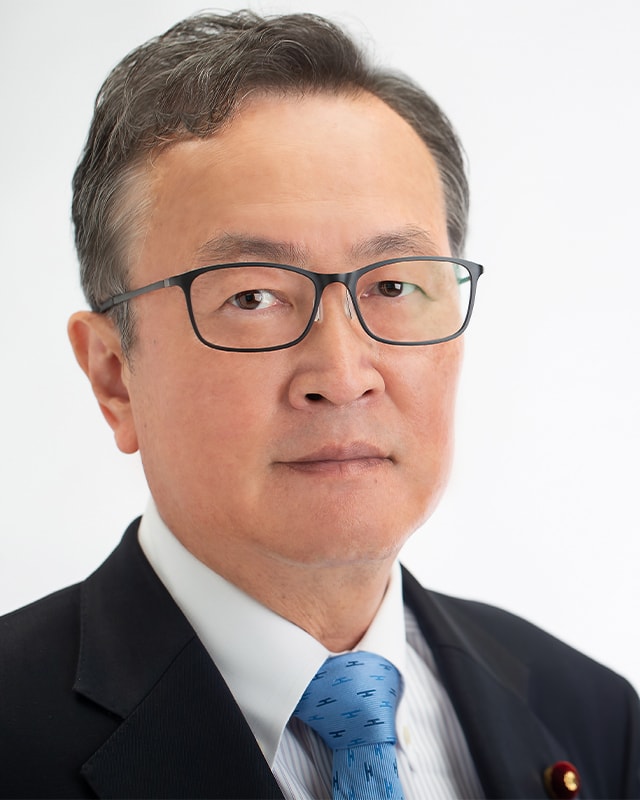
全84件 / 9ページ
2024-12-19
第216回国会(臨時会) 衆議院 憲法審査会 第1号 発言No.36全文を見る今、津村議員から御指摘いただいた点でございますが、平成二十四年の自民党の憲法草案でございます。この扱いにつきましては、確かに自民党の中でのオーソライズはしたものでございますが、その後、様々な検討を行いましたところ、この二十四年の草案については、ある意味では歴史的文書ということで凍結をしている、そういう現状にあります。そして、その後、我々は、先ほども申し上げましたけれども、四項目についての緊急に取り組むべき課題ということで、それを提案をしているという状況でありますので、平成二十四年の草案にはこだわらない、そういう状況、今自民党の中では対応しております。
ただ、私個人的には、やはりこの問題については確かにいろいろな解釈がございますので、その点についてこの憲法審査会で議論することについてはやぶさかではない、皆様としっかり議論していきたいと思っております。
以上です。
2024-12-19
第216回国会(臨時会) 衆議院 安全保障委員会 第4号 発言No.150全文を見る公明党の西園勝秀です。
初めての国会質問となります。どうぞよろしくお願いいたします。
二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない、いかなる暴力の威嚇や行使も国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならない、さきの大戦への深い悔悟の念とともに、我が国はそう誓いました。法の支配を重んじ、ひたすら不戦の誓いを堅持してまいりました。
明年は、戦争終結から八十年の節目となります。しかし、中谷防衛大臣が所信表明演説で述べられたように、中国軍機による領空侵犯、北朝鮮による弾道ミサイル発射、ロシアの活発な軍事活動など、今、我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しく複雑なものとなっています。
そのような中、戦争放棄を定めた平和憲法を有する我が国は緊迫するこの国際情勢にどのように対処すべきか。まずは、防衛力の規模の観点から質問させていただきます。
中谷防衛大臣にお伺いします。二〇二四年度の防衛予算は対GDP比約一・六%ですが、国家安全保障戦略の中ではこれを二%まで引き上げるとされています。なぜ二%まで引き上げる必要があるのでしょうか。理由をお聞かせください。
2024-12-19
第216回国会(臨時会) 衆議院 憲法審査会 第1号 発言No.4全文を見るこの際、御報告申し上げます。
去る十三日の幹事会におきまして、お手元に配付のとおり「憲法審査会の運営に関する申合せ」を決定いたしましたので、私から申し上げます。
憲法審査会の運営に関する申合せ
憲法調査会以来の先例を踏まえ、次のように申し合わせる。
一 会長が会長代理を指名し、会長の所属会派を除き委員数が最も多い会派の幹事の中から選定する。
二 幹事の割当てのない会派の委員についても、オブザーバーとして、幹事会等における出席及び発言について、幹事と同等の扱いとする。
以上でございます。
この際、この申合せに基づき、会長は、会長代理に自由民主党・無所属の会所属幹事船田元さんを指名いたします。
2024-12-19
第216回国会(臨時会) 衆議院 憲法審査会 第1号 発言No.5全文を見る2024-12-19
第216回国会(臨時会) 衆議院 憲法審査会 第1号 発言No.9全文を見る自由民主党の船田元であります。
自民党を代表しまして、今後の憲法審査会の議論の進め方等について意見を述べたいと思います。
その前に、先ほど橘衆議院法制局長から、これまでの憲法をめぐる様々な議論と経過をお話をいただきまして、私も何回か登場いたしまして、大変身の引き締まる思いであります。また同時に、幾つものハードルがあり、それを一つ一つ乗り越えてきた、このことにつきまして、感無量の部分もありますが、同時に、新たに、身を引き締めてこの問題に対処しなければいけない、そういう新たな気持ちも湧き上がってまいりました。
まず、国会での憲法論議においてよく取り上げられております、先ほどもお話のありました中山方式について、私の私見を申し上げます。
中山方式は、憲法調査会長、憲法調査特別委員長を歴任された中山太郎先生が提示をされた理念、そしてこれに基づく運営を表すものであります。すなわち、憲法に関する議論に政局を絡めず、少数会派の声も尊重しつつ、与野党の別なくお互いに譲り合って合意形成を目指すものであると理解をしております。
ただ、こうした理念にもかかわらず、例えば平成十九年の国民投票法の制定時における混乱を始めとして、憲法に関する議論がこれまで何度も政局に巻き込まれてきたことは、大いに反省をしなければなりません。
この点について枝野会長は、先日の会長就任の御挨拶におきまして、この中山方式の本質に立ち返らなければいけない、こう発言されており、私もこれには賛同したいと思います。今後も政局から離れた静かな環境の下で憲法に関する議論が着実に行われることを期待し、私も会長代理として枝野会長とともに環境整備に努めていきたいと思っております。
自民党は、党内の憲法論議として、平成十七年、そして平成二十四年、二回にわたりまして憲法改正草案をまとめてまいりました。
その上で、現在、自民党が優先的に取り組むべき憲法改正のテーマとして掲げておりますのは、自衛隊の明記、緊急事態対応、地方公共団体や参議院合区解消、教育充実、この四項目でありまして、この四項目につきましては、平成三十年に、条文イメージたたき台素案として公表したところであります。
ただ、この条文イメージは、完成された条文ではなく、あくまでもたたき台素案でありまして、憲法審査会における議論や各党、有識者の意見を踏まえ、幅広い合意を得て憲法改正原案の提出を目指すものと考えています。
この四項目のうち、特に緊急事態対応につきましては、憲法審査会において議論が大きく進展をしております。
具体的には、令和四年常会以降、議論が継続的に行われ、同年十二月に一度目、それから昨年六月に二度目の論点整理が行われました。さらに、さきの常会終盤におきましては、当時の中谷筆頭幹事が、五会派の共通認識の整理として、公明、維新、国民、有志の先生方のアドバイスを踏まえて作成した資料を配付し、選挙困難事態における国会機能維持条項に盛り込むことが考えられる事項の骨格について発言をされました。
さらに、その後、中谷筆頭幹事から、これをより詳細にした資料が公表されております。この資料では、その内容が条文に近い形で提示されているとともに、今後議論すべき課題についても整理されておりまして、これまでの議論の到達点はほぼこの資料に集約されていると考えます。今後の審査会においては、まずこれを発射台として、このテーマについて優先的に議論を進めていくべきである、このように考えています。
なお、先日、韓国で発出されました戒厳令、非常戒厳、これを引き合いに、緊急事態条項には濫用のおそれがあり、憲法に緊急事態条項を設けるべきではないと言われることもしばしばございますが、韓国の戒厳令と我々が行っている議論とは全く別物と考えています。
我々が議論している、いわゆる議員任期の延長を中心とした緊急事態条項は、いかなる緊急時であっても国会機能を維持し、国民の生命、身体、財産を守るための法律の制定や予算の議決ができるようにするための仕組みをつくっていこうというものであります。韓国の戒厳令のように政治活動を禁止したり報道や集会を規制したりするといったものとは全く性質が異なります。
さらに、国民投票法の議論も必要であると思います。令和三年改正の際に、投票環境の整備と投票の公平公正の確保について検討する旨規定されましたが、その検討期限が既に経過をしてしまいました。
まず、投票環境の整備に関しましては、衆議院の解散により廃案となってしまいましたが、公選法並びの国民投票法改正を速やかに行う必要があると思います。
また、投票の公平公正の確保につきましては、テレビCM、ネットを用いた広告や意見表明の在り方について様々な意見が出されております。
私個人としては、テレビCMの禁止強化、運動費用の上限規制、ネットを用いた広告や意見広告の直接規制というよりも、国民投票運動はできるだけ自由にとの国民投票法制定当時の趣旨を踏まえまして、事業者等の自主規制や間接的な方法による規制を中心に検討すべきではないかと思います。その間接的な方法としては、例えば、民放各社からCM考査の状況を広報協議会に定期的に報告をしてもらうなどの方法も考えられます。
また、フェイクニュースへの対応も含め、委員の皆様と議論を深めていきたいと思っております。国民投票の公平公正を確保する上で、国民投票広報協議会の役割は極めて重要であると思います。その役割や諸規程の整備についても議論を進めていきたいと思っております。
衆議院憲法審査会では、ほぼ毎週の定例日開催が定着をし、丁寧な議論が積み重ねられてきていると思います。先ほど申し上げました選挙困難事態における国会機能維持条項のように、議論が煮詰まってきているテーマもございます。今後は、議論を拡散させることなく、テーマを絞って、精力的に議論を集約していかなければいけないと考えます。皆様の活発な、かつ建設的な議論を期待いたしまして、発言といたします。
2024-12-19
第216回国会(臨時会) 衆議院 憲法審査会 第1号 発言No.6全文を見る衆議院法制局の橘でございます。
本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方からの御指示によりまして、冒頭の御報告をさせていただくことになりました。どうかよろしくお願い申し上げます。
私自身、二〇〇〇年一月以来、約四半世紀にわたって、各党各会派の先生方の御指導を頂戴しながら、衆議院及び各党の憲法論議を拝聴し、また、お手伝いをさせていただいてまいりました。本日の御報告は、門前の小僧よろしく、この間に見聞きしたことを踏まえて、客観的な事実関係を整理して御報告申し上げるつもりでございますが、至らざる点も多々あると思います。何とぞ御容赦くださいますよう、あらかじめお願い申し上げます。
お手元に、吉澤事務局長ら衆議院憲法審査会事務局の皆さんと共同で作成させていただきましたスライド及び資料を配付させていただいております。これに沿って御説明申し上げたいと存じます。
早速ですが、目次をおめくりいただきまして、スライド一ページを御覧ください。
まず、衆議院憲法審査会における憲法論議の経過を御理解いただく前提として、二〇〇〇年一月に設置されました憲法調査会とそこでの運営ルールについて言及しておきたいと存じます。
憲法調査会は、日本国憲法の下、憲法改正の発議権を有する国会に初めて設置された憲法論議の専門機関です。その背景には、国際的には、一九八九年のベルリンの壁崩壊や九〇年の湾岸戦争に始まる冷戦構造の終えんが、また国内的には、一九九三年の五五年体制の崩壊と八会派による細川連立政権の誕生に象徴される政党の流動化といった政治状況がございました。
このように世の中が大きく変わる中で、改めて国家の基本法たる憲法を見詰め直そうと、一九九七年に、超党派の憲法調査委員会設置推進議員連盟が結成されました。その活動によって、二〇〇〇年一月、憲法調査会が設置されたのでございます。ただ、いきなり憲法改正の議論に進むのではなく、あくまでも調査専門の機関とされ、憲法改正の提案権などは持たないこととされたのでした。
その調査会長に就いたのが、湾岸戦争時の外務大臣であり、同議連の会長でいらっしゃった中山太郎先生でございます。
ここで、スライド二ページを御覧ください。
中山会長は、憲法は政権を相争う政策論争を行う民主主義の土俵それ自体であり、その土俵づくりともいうべき憲法論議には与党も野党もない、国会議員一人一人が、国民代表として、政局を離れた静ひつな環境の下で大所高所からの議論を行うべきとの信念から、第一に、政局から一定の距離を持って運営すること、第二に、野党第一党の幹事を会長代理とし、会長とともに調査会運営に責任を持つこと、第三に、憲法の理念である少数意見尊重に鑑みて、基本的に数が物を言う国会ではあるが、少数会派の発言権をできるだけ保障することといった原則を打ち立てられました。
これが後に中山ルールとか中山方式と言われる運営ルールですが、その根底にある基本的な考え方は、次のようなものでした。
憲法論議、特に、その一つの到達点である憲法改正は、多様な価値観を有する人々、全国民の生活に影響するものであるから、それぞれが信ずる理想を追求しつつも、決してそれに拘泥してはならない、皆が少しずつ譲り合い、歩み寄りながら、妥協して作り上げていくものだという考え方です。中山会長のお言葉をかりれば、偉大なる妥協、グレートコンプロマイズの姿勢であり、これこそが合意形成の肝であると述べておられました。
この中山会長を一貫して支えられたのが、歴代の会長代理である、民主党の鹿野道彦先生、中野寛成先生、仙谷由人先生、そして枝野幸男先生であり、与党筆頭幹事でいらっしゃった葉梨信行先生、船田元先生でした。中野寛成先生はこの中山ルールを、与党は度量を、野党は良識を持てと表現されました。
恐縮ですが、再びスライド一ページにお戻りください。
この中山調査会は、二〇〇五年四月に、五年間の調査結果をまとめた七百ページを超える報告書を発表しました。その中に、戦後六十年間制定されてこなかった最も基本的な憲法附属法規である憲法改正国民投票法、これを速やかに制定するべきであるとの提言が盛り込まれました。
スライド三ページを御覧ください。
この提言に基づいて設置されたのが、憲法調査特別委員会です。この特別委員長にも中山太郎先生が就任されました。
この特別委員会で国民投票法制定に向けた議論を開始するに当たって、野党筆頭理事であった枝野先生は、憲法改正国民投票法は、形式的には法律の一つにすぎないが、その制定プロセス、すなわち制定過程における合意形成のプロセスは、近い将来の憲法改正の予行演習、リハーサルのようなものにしたいと考えました。この基本姿勢は、中山会長始め与野党の理事、委員にも共有され、委員会採決の最終局面までそのとおりに進んでいきました。
しかし、二〇〇七年七月の参議院選挙を前にした与野党対立の政局に巻き込まれる形で、それまで築き上げてきた委員会の現場での合意は、同年四月十二日の特別委員会の採決直前に崩壊し、同日の採決は、与党による強行採決の形になってしまいました。枝野先生は、採決当日に、党内をまとめ切れなかった責任を取って理事を辞任されました。
ただし、可決された法案の内容は、それまでの議論の過程で与野党が合意してきた事項をそのまま盛り込んだもので、自民・公明案と民主案を合体した併合修正案という珍しい形を取ったものでした。
しかし、強行採決のしこりと、その直後の参議院選挙によるねじれ国会の誕生によって、その後四年三か月の長きにわたって衆議院の憲法論議は停滞することになりました。
次に、スライド四ページを御覧ください。
このような経緯を引きずりながらも、民主党への政権交代が行われた後の二〇一一年十月、国民投票法による改正国会法に定められていた憲法審査会がようやく始動することになります。
初代の審査会長に就任した大畠章宏先生は、中山ルールを踏襲することを宣言し、まず、政界を引退されていた中山太郎先生を参考人として招致した上で、二〇〇五年の中山調査会報告書を復習、レビューするところから議論を始められました。
この大畠審査会の基本姿勢は、再度の政権交代を挟んで就任された保利耕輔会長にも引き継がれました。選挙で中断した中山調査会報告書のレビューを続けるとともに、国民投票法制定の際に残されていた三つの宿題にも取り組んだのです。
三つの宿題とは、一つ目は、憲法改正国民投票の十八歳投票権に合わせて、選挙権年齢も十八歳に引き下げること、併せて民法の成年年齢も引き下げること、二つ目は、憲法改正国民投票は主権者国民としての貴重な意思表明の機会であり、そもそも公務員制度それ自体の土俵でもあるのだから、公務員も、賛否の表明など一定の政治的行為ができるような法整備をすること、三つ目は、憲法改正国民投票以外の一般的な国民投票制度についても、現行憲法の下でどこまでが可能か検討すること、この三つです。
このうち十八歳選挙権については、二〇一四年六月の国民投票法改正と翌二〇一五年六月の公選法改正の二段階の法改正を経て実現されました。さらに、成年年齢引下げのための民法改正案も、上川陽子法務大臣の下で二〇一八年に成立し、既に二〇二二年四月から施行されております。公務員の政治的行為についても、二〇一四年の国民投票法改正で措置されましたし、一般的国民投票制度についても、新たな検討条項が設けられています。
次に、スライド五ページを御覧ください。
その後、二〇一四年十二月の第二次安倍政権下での衆議院解散・総選挙、二〇一六年七月の参議院通常選挙などを挟んで、衆議院憲法審査会での憲法論議は大きな転換期を迎えることになりました。
与党及び改憲に積極的な会派が衆参共に三分の二を超える勢力を獲得し、これを背景として憲法改正に大きな弾みがつくのではと期待する声が上がる一方、野党の一部には、これに反発する形で、憲法論議それ自体に強い警戒心が芽生えていったのでした。
この時期の政治の現場での主な出来事を振り返りますと、まず、政府・自民党を中心とした動きとしては、解散・総選挙前の二〇一四年七月の憲法九条の解釈変更、それに基づく翌二〇一五年の平和安全法制をめぐる与野党の激しい憲法論議、二〇一七年五月三日の読売新聞紙上での安倍総理・総裁の自衛隊明記、緊急事態対応、教育充実の三項目御発言があり、そして、この三項目に合区解消・地方公共団体を加えた四項目の憲法改正の条文イメージたたき台素案が、翌二〇一八年三月の自民党大会で報告、了承されております。
野党に目を転じますと、二〇一六年三月には、当時のおおさか維新の会が、教育無償化、憲法裁判所、道州制導入を始めとする統治機構改革の三項目の憲法改正原案を発表し、国民民主党も、二〇二〇年十二月に、デジタル時代の人権保障と統治機構の再構築を通じて、憲法の規範力を高めるための、憲法改正に向けた論点整理を発表しております。
また、民主党、民進党におかれましても、二〇一七年総選挙直前の旧立憲民主党の結成と、その三年後の旧国民民主党との合流による新立憲民主党の誕生を踏まえて、その両者の憲法観をすり合わせ、確認した、憲法論議の指針といった基本的な文書が策定されています。この指針では、安保法制は違憲であること、自衛隊明記には反対であることを明確に打ち出すとともに、統治機構の分野では、臨時会召集期限の明記や解散権の制限、人権の分野では、知る権利や、同性婚、LGBTの人権などに言及されています。
このように、この時期の憲法論議は、与野党の対決ムードの高まりの中で政治的、政局的なテーマとなっていきましたが、それと反比例するかのように、憲法審査会での議論は停滞し、その開催自体に汗を流さなければならない時代に入っていったのでありました。
しかし、そのような中にあっても、森英介会長や佐藤勉会長の下、与野党の会長代理や幹事の先生方は、中山ルールを念頭に置きながらも、新たな与野党の向き合い方に腐心され、憲法公布七十年を機にとか、海外調査報告書を機にといったきっかけを探りながら、お互いに合意できるテーマを設定して、審査会の開催に向けて努力されたのでありました。
この時期のもう一つのテーマとして、国民投票法の改正問題がございます。二〇〇七年の国民投票法制定から十数年を経る間に、公選法においては、在外投票システムの改善や共通投票所の開設、洋上投票の機会拡充など、投票環境向上のための法改正が次々と施されていました。投票や開票のシステムは国民投票法でも同じであり、同様にバージョンアップしていく必要性が認識され、提出から成立までかなり時間はかかりましたが、二〇二一年六月に、公選法並びの七項目改正案が成立しております。
次に、スライド六ページを御覧ください。
衆議院憲法審査会の議論において更なる転換点となったのが、二〇二二年の通常国会からの議論でした。
再び会長職に就かれた森英介会長の公正中立、円満かつ筋を通した毅然たる運営方針の下、与党筆頭となってから三年余りの間、与野党合意に基づく審査会開催に腐心されてきた新藤義孝先生と野党筆頭に就任されたばかりの奥野総一郎先生との御協議によって、衆議院予算委員会が開会中の二月の段階から、毎週木曜日の定例日に憲法審査会を開催して、継続的に議論が行われるようになっていったのです。
当時の新藤先生のお言葉をかりると、憲法審査会の開会自体がニュースになるようじゃ駄目だ、その議論の中身を国民に伝えてもらえるようにならないといけない。この時期の議論の転換を表した象徴的なお言葉だと拝察いたします。
当時は、二〇二〇年の新型コロナウイルスの感染者発生から三年目に入っており、衆議院では、本会議のいわゆる間引き出席など、三密を回避しながら国会を機能させる工夫がなされていました。
そこで、最初に議論の俎上に上ったのが、憲法五十六条一項の定足数を定める「出席」の概念にオンラインによる出席も含まれるのかといった論点でした。議員間討議や法制局による論点説明、参考人質疑を踏まえた上で、同年三月三日、審査会で次のような決議がなされました。
憲法五十六条一項の「出席」は、原則的には物理的出席と解するべきではあるが、国会の機能を維持するため、緊急事態が発生した場合等においてどうしても本会議の開催が必要と認められるときは、例外的にオンライン出席も含まれると解釈することができる、これが本審査会における議論の大勢であったというものです。詳細は資料1を御参照ください。
この決議は、森会長から当時の細田博之議長に報告され、細田議長の指示で、山口議運委員長の下で議論が開始されました。そして、本年六月、その成果の一つとして衆議院規則が改正され、委員会レベルでのオンライン参考人が正式に認められることになったのでした。
さて、一昨年の通常国会では、このオンライン審議の議論に続いて、緊急事態一般の議論に入っていくことになりました。同年二月二十四日のロシアによる突然のウクライナ侵略という事象を目の当たりにして、このような事態への備えに関する認識が多くの委員間で共有されていったからであります。
そして、当時の審査会での議論は、次のような形で進んでいきました。
まず、ステップ1、各委員からテーマ選定のための自由な発言をしてもらう。次にステップ2、その委員発言を整理して、共通の関心事項と思われるテーマを選定して、これについて議論を進める。そしてステップ3、当該テーマに関する議論の積み重ねを踏まえて、法制局及び審査会事務局に論点整理をしてもらう。ステップ4は、この論点整理を踏まえて、また、必要に応じて参考人質疑を行うなどして、更に議論を深めていくといったプロセスです。そして最終的には、ステップ5、この議論の結果、憲法改正が必要と判断されれば、具体的な条文案の作成に入っていくことになります。
緊急事態条項については、法制局、審査会事務局による論点整理、参考人質疑とそれを踏まえた議論の深掘りの段階、今申し上げたステップ4まで進んでいきました。この論点整理の詳細は、資料2を御参照ください。
その結果、自民、公明、維新、国民、有志の五会派の委員においては、大規模自然災害や異常な感染症、テロや有事などの場合においても行政監視を始めとする国会機能を維持するために、長期間、国政選挙の実施が困難と見込まれる場合には、議員任期の延長や解散権制限を定めておくことが望ましいといった、いわゆる選挙困難事態における国会機能維持条項、この必要性が述べられ、速やかに条文案作成のステージに入っていくべきである、このような発言が相次ぎました。
これに対して、立憲、共産の先生方からは、国会機能の維持に限ったとしても、そのような条項には濫用のおそれがある、国会機能の維持は現行憲法の参議院の緊急集会で対応可能であるとの意見が述べられたところです。
他方、この時期のもう一つの重要なテーマに、ネットやデジタル化への対応問題があります。
具体的には、国民投票の公正確保のために、放送CMをはるかに凌駕するに至ったネットCMや、SNSなどにおけるフェイクニュースなどにどのように対応していくべきか、そもそも規制できるのかといった議論です。
加えて、このデジタル化やフェイクニュースの問題は、国民投票の場面に限らず、情報アクセス権やプライバシー権、情報的健康といった憲法上の人権保障の問題でもあることが認識されるようになってまいりました。
これらの論点については、参考人として招致した、ネット社会と憲法の第一人者である慶応義塾大学の山本龍彦先生や、ネット業界、ファクトチェック団体の代表者の方々との質疑応答によって議論が深まりつつあるところです。
最後に、スライド七ページを御覧ください。
以上の議論は、今年の常会に入っても続けられました。すなわち、一方では、緊急事態における国会機能維持のための条文案の作成に関する議論が、他方では、国民投票法の議論やデジタル時代の人権保障の議論が唱えられ、活発な意見交換が行われてきているところです。
以上、衆議院憲法審査会における憲法論議について、設置以来今日までの大ざっぱな流れを御報告させていただきました。
お耳汚しで大変失礼申し上げました。御清聴ありがとうございました。
2024-12-19
第216回国会(臨時会) 衆議院 憲法審査会 第1号 発言No.11全文を見る立憲民主党、武正公一です。
憲法審査会の運営、議論の進め方について申し述べたいと思います。
国民投票法改正案に対して、立憲民主党は、附則第四条が求める法制上の措置には、国民投票の公平及び公正を確保するための措置を講ずるものとあることから、その点も法改正に盛り込むべきと主張してきた。法施行後三年の見直しを本年九月十八日に迎えたことから、最優先で取り組むべき課題と考える。
ネット広告の飛躍的増加、ネットを通した世論操作、広告放送の量的自主規制を行わないとの民放連の発言などの事情変更を踏まえ、国民投票法改正案に次のような事項を検討すべきである。一、憲法改正案に対する賛否の勧誘のための広告放送の全面禁止、二、政党等による賛否の意見表明のための広告放送の禁止、三、政党等によるインターネット有料広告の禁止などである。
さらに、選挙におけるネット、SNSによる誤・偽情報、いわゆるフェイク情報の拡散といった問題に対応するため、一、憲法改正案に関するタウンミーティングの開催、二、インターネット等を利用する方法による広報の二項目を広報協議会の事務に追加することも検討すべきである。また、フェイク情報の流布に対応するため、ファクトチェックを行う民間団体等と広報協議会との連携に関する規定についても検討すべきである。
最近の選挙では選挙妨害や選挙運動用ポスターなどに関わる問題に対して法整備の必要性が指摘される一方、選挙運動や表現の自由の保障も重要である。そこで、表現の自由や選挙運動の自由の意義と、制約の可否や程度について、憲法の観点から議論すべきであると考える。
次に、衆議院の解散に際し、時の内閣による恣意的な権限行使が繰り返されている。政府解釈では党利党略による解散権の行使は許されないとされており、このような恣意的な権限行使は、憲法上、到底許されるものではない。
在外日本人選挙権訴訟違憲判決より、可能な限り在外投票の機会を確保すべきというのが憲法の要請と考える。しかし、今回の衆議院選挙の解散では、投票所入場券が届くのが特に大都市を中心に遅れて、期日前投票に影響が出、結果、投票率は戦後三番目の低さになり、在外投票率も一%台と言われる。解散から選挙期日までの期間が短いことは選挙権の行使に支障を生じさせており、国民の権利を侵害していると言える。
立憲民主党は、衆議院の解散は、一、憲法六十九条に規定する場合のほか、二、直近の衆議院総選挙後に浮上した国政上の重要な争点について国民の判断を仰ぐべき場合などに限定することを提案する。加えて、衆議院を解散する場合には、内閣は解散の予定日と理由を衆議院に通知し、本会議で質疑を行うことを義務化することで、恣意的な解散を抑制することができると考える。以上の解決方法について議論を進めるべきである。
さらに、憲法第五十三条による内閣の臨時国会召集は憲法上の法的義務であり、内閣は合理的期間内に臨時国会召集を決定しなければならないとするのが、政府、学説のいずれにおいても確立した見解である。ところが、諸内閣が臨時国会召集を放置する憲法違反の繰り返しが常態化している。同規定の趣旨を踏まえ、臨時国会召集の要求があった場合、二十日以内に臨時国会を開会するなど、必要な法制上の措置を議論するべきだ。
また、憲法審査会の目的には、「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査」がある。同性婚訴訟は、今年に入って三つの高等裁判所で違憲判決が出た。同性婚を認めない民法などの規定が憲法十四条一項の法の下の平等や二十四条二項の個人の尊厳と両性の本質的平等に反するとしたほか、福岡高裁では、十三条の幸福追求権にも反すると判断された。裁判所は同性婚の法制化を立法府に求めており、違憲判決が相次いでいることから、同性婚の法制化について国会で議論をすべきである。
法人の人権については、八幡製鉄事件では、法人の人権享有主体性を権利の性質上可能な限り認め、法人は政治資金の寄附など政治的行為をなす自由を有するとしている。その上で、巨額の寄附による金権政治といった問題点への対処は立法政策で解決すべきものとしており、法律により企業の政治活動の自由を制限することは可能であると解される。また、南九州税理士政治献金事件では、強制加入団体による政治資金の寄附は目的の範囲外であるとしている。このような判例を踏まえ、法人の政治活動の自由に関し、今臨時国会でも衆議院予算委員会で石破総理の発言もあり、議論を深めるべきと考える。
また、サイバー攻撃に対して常時パトロールを行う積極的、能動的サイバー防御が必要とされる一方、通信の秘密が制約される可能性も考えられる。通信の秘密を最大限保障する観点から、能動的サイバー防御の導入に際し想定される具体的事例と制約の可否について、ヒアリングや議論を行うべきである。
信教の自由は個人の価値観の根源であり、手厚く保障されるべきである。一方、旧統一教会などの問題から、カルト宗教への対策の必要性も指摘されている。そこで、信教の自由に関する判例などに関するヒアリングを行い、信教の自由の制約の可否や程度について議論すべきである。
ほか、立憲民主党憲法論議の指針の下に臨んでまいりたい。
最後に、衆議院議員選挙も終え、憲法審査会の進め方は、新しい議員を多く迎え、各党各会派での意見集約、情報共有を前提に、党会派を代表しての意見を述べ、質疑を行い、憲法審査会での議論を丁寧に、そして闊達に進める必要がある。
以上です。
2024-12-19
第216回国会(臨時会) 衆議院 憲法審査会 第1号 発言No.13全文を見る日本維新の会の馬場伸幸です。
先ほど橘法制局長より、衆参両院における憲法審査会の原点となった超党派の憲法調査委員会設置推進議員連盟結成から今日まで二十七年間の憲法論議の経過について、るる御説明いただきました。ありがとうございました。
議連の立ち上げから衆参両院での憲法調査会設置に奔走し、本院調査会の初代会長を務めた、私の師匠、中山太郎先生にいま一度思いをはせています。
湾岸戦争当時外務大臣だった中山先生は、お金だけ出して人的貢献をしなかった我が国に対する諸外国の冷たい視線を痛感しました。その根因は施行から半世紀を経た旧時代の日本国憲法にあると考え、たまらず行動に移されました。
中山先生が全国会議員に配付した議連の設立趣意書にはこう書かれています。憲法論議は国権の最高機関たる国会において党派を超えた全国民的立場でなされるべきであり、国家の基本問題について真摯に議論することこそが我々政治家に課せられた最大の使命だ。立法府に身を置く我々はこの言葉をかみしめるべきです。
ほぼ開かずの扉状態だった本審査会も、ここ三年は、私たちの強いプッシュもあって相当数開催されるようになりましたが、中身は羅針盤のない航海のごときです。各会派の意見発表会から脱却できず、いざ意見集約に向けてアクセルを踏もうとすれば、特定野党がいわゆる中山方式を曲解、悪用し、ブレーキをかけてきました。
弟子だった私が中山方式の真髄をはっきり申し上げます。中山方式イコール全会一致ではありません。中山先生が先頭に立たれていた当時は、まず憲法改正という列車をレールに乗せなければならないフェーズでした。中山方式は、時間をかけてでも中身の議論をするための紳士協定ですが、もはやフェーズは変わりました。レールに乗った列車を前に進めなければなりません。
改憲につながるやり方は一切認めないと繰り返す共産党が存在する限り、全会一致は永遠に望めません。反対会派の意見に耳を傾けることは不可欠ですが、どこかで議論に区切りをつけ、多数決で結論を得ることが民主主義の原則です。
中山方式が反映された本審査会の会長代理制度には、与野党双方が審査会の運営に責任を持つという思いが込められています。野党第一党として長らく会長代理の椅子に座ってきた旧民主党や立憲民主党の方々は、果たしてその責任を全うしてきたと胸を張れるのでしょうか。政局に絡めないとする中山方式を口にするなら、しっかりと責任を果たしていただきたいと思います。
解散・総選挙もあり、本審査会での実質討議は六月十三日以来のことです。既に半年間の空白ができました。昨年十二月七日には、当時の中谷与党筆頭幹事から、改正原案の起草に向けた機関を創設する旨提案がありましたが、この一年、一ミリも進んでいません。今国会での審査会開催は、本日が最後です。放っておいたら、年明けの通常国会開会後も、予算審議が終わるまで審査会を開かないという立法府の因習から、少なくとも三月初めまで実質休眠状態になることは目に見えています。起草委員会の設置どころではありません。
枝野会長を始め、皆さんに訴えます。衆議院憲法審査会規程によると、閉会中でも手続の必要なく開催ができます。悠長に通常国会の開会を待つのではなく、年末年始の閉会中も審査会を適時開いて、議論を前に進めようではありませんか。
総選挙を経て委員の構成が変わっても、これまでの審査会での議論の積み上げを無にしてはならないことは言うまでもありません。
本審査会での実質討議は、令和四年が一年間で二十回、五年が一年間で十九回、今年が本日を含めて十回、この三年間で計四十九回行われましたが、議論の大半が、非常事態時の国会議員の任期延長、国会機能の維持などを規定する緊急事態条項の創設に費やされたと認識しています。既に論点は出尽くしています。
日本維新の会は、昨年六月、国民民主党、有志の会の皆さんとともに緊急事態条項の条文案を策定しました。この条文案について、西修駒沢大学名誉教授は、四月に上梓した著書「憲法一代記」で、非常に優れた規定方式だと高く評価され、これを土台に自民、公明両党が参画し、細部を詰めるのが最も妥当で最善の策であると指摘されています。方向性は、自民、公明両党と大きなそごがないと認識しています。
私たちは、三会派の条文案を本審査会で議論の俎上にのせるように訴えてきましたが、条文案や資料の提出は認められないとの申合せにより、一年半塩漬けにされたままです。
枝野会長には、是非、このような理不尽なルールは改め、直ちに起草委員会を設け、自民、公明だけでなく、立憲民主党など他会派にも緊急事態条項の条文案の合意形成に参画するよう差配していただきたく存じます。
中山先生は、憲法論議には偉大なる妥協が必要だとも訴えておられました。議論に加わった会派の一部が納得できなくても、機が熟せば、民主的な多数決によって公明正大にゴールへの歩みを進めるべきです。
一方、来年の結党七十年に向け憲法改正実現へ先頭に立たれている石破総理・総裁は、十月の臨時国会の所信表明演説で、国会発議の目標について、総理在任中と明言されましたが、なぜか今国会での所信表明演説と代表質問答弁では目標期限が消えました。釈然としません。
この間、自民党は、本審査会長ポストを立憲民主党に明け渡しました。まさか憲法改正に白旗を上げたわけではないでしょうが、これまで同様、やるやるとポーズを繕うだけなら、党本部に高らかに掲げている憲法改正実現本部の看板をさっさと下ろしてください。そう責められたくないなら、いいかげん、行動で示していただきたい。
本院は、少数与党となり、国会発議のための三分の二の賛成確保が厳しい情勢であることは承知しています。とはいえ、立憲主義、民主主義の根幹には国民主権があります。その国民主権を具現化することこそ、憲法改正の国民投票です。主権喪失の下で作られた憲法が抱える諸課題を乗り越え、憲法を国民の手に取り戻すときです。
枝野審査会長は、十二日付毎日新聞のインタビューで、しっかりと建設的な議論ができるよう努力したいと決意を表明されました。党利党略によって建設的な議論が不当にブロックされる事態を招かぬよう、審査会長としての責務を全うしていただくよう強く求めて、私の発言を終わります。
2024-12-19
第216回国会(臨時会) 衆議院 憲法審査会 第1号 発言No.15全文を見る国民民主党の浅野哲です。
本日は、衆議院憲法審査会での初めての発言となりますので、まず一言御挨拶させていただきます。
枝野会長、船田、武正両筆頭幹事のリーダーシップの下、委員各位の皆様と真摯かつ建設的な議論に臨んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
先般の枝野会長の言葉をおかりすれば、日本国憲法は、国の在り方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の根拠となり基本を成すものです。重要な憲法を扱う場に立つ重責を深く感じるとともに、丁寧で慎重な議論を重ねていく必要性を改めて実感しています。
ところで、直近の憲法審査会において主に取り扱われてきた事項として挙げられるのが、選挙困難事態における国会機能の維持、そして、国民投票に係るCM規制の在り方の二点です。
国権の最高機関たる国会をいかに維持するか、そして、我が国の最高法規たる憲法の改正手続の公正性をいかに確保するか。いずれも、憲法の趣旨を変えるためではなく、あくまでも憲法の趣旨をいかに守るかという視点で議論が進められてきたものと承知をしています。
まず、最も充実した議論を重ねてきた選挙困難事態における国会機能維持に関する議論についてですが、昨年六月十九日に発表させていただいた日本維新の会、有志の会、国民民主党三会派による憲法改正に向けた条文案、そして、この条文案を踏まえて自民党、公明党も入れた五会派の合意を得て六月十三日の憲法審査会で中谷筆頭幹事が提示したいわゆる中谷メモに基づき、今後、橘局長の言葉をかりれば、ステージ5、すなわち、要綱案の作成や条文化作業が本審査会で進められることを強く求めます。そのためにも、早急に起草委員会を設置して協議を開始することを求めます。
なお、選挙困難事態における国会機能維持に関しては、参議院側から幾つかの課題が指摘されていることを受け、各論点について参議院の憲法審査委員と合同の審査会を開催するなどしながら、議論を深めていくことも提案します。
他方、国民投票に係るCM規制の在り方については、本審査会での集中した議論が必要と考えます。
二〇一六年の米国大統領選挙でのケンブリッジ・アナリティカ事件を始め、近年、国内外でも散見されているSNSやインターネット上でのフェイクニュースの流布を含めた世論誘導行為、あるいは第三者による収益化行動の顕在化、さらにはサイバー攻撃といったリスクが深刻化している現状は看過できません。広報協議会にファクトチェック機能を持たせるかガイドラインを作成する権能を持たせるなど、現実的かつ実効的な制度設計の議論を深めていきたいと思います。
以上に申し上げたように、憲法審査会がこれまで積み重ねてきた議論の状況を踏まえれば、選挙困難事態における国会機能維持のための議論と国民投票に係るネットCM規制の在り方についての議論は共に引き続き本審査会で取り扱うべきであり、また、その重要性や緊急性を鑑みれば、憲法審査会は定例日である毎週木曜日に開催することを求めます。
最後に、前回の発言の中で枝野会長は、中山方式に立ち返るとおっしゃいました。私もいわゆる中山方式の考え方に共感する者の一人であります。平成十二年から十七年まで開催された憲法調査会は、小委員会や公聴会を含め、延べ百三十六回開催されました。
最終回であった平成十七年四月十五日、憲法調査会での報告書に関する採決前の発言の一部を引用します。「本調査報告書の作成を一つのスタートラインとして、本調査会が、憲法議論の深化と憲法改正手続法制の整備の役割を担う第二ステップに進み、充実した議論がさらに展開することを強く望みます。」これは、当時会長代行であった枝野会長の言葉であります。
あれから約二十年を経て、憲法調査会は憲法審査会へとその名称と役割を変え、現在までに様々な議論が積み重ねられてきました。我々は、枝野会長の下においては、充実した議論を更に展開し、起草委員会設置や条文化作業等のネクストステップへ進む議論が行われることを強く望んでおります。
それぞれの会派ごとに考え方の相違点があるのは当たり前ですが、そのような状況を前提としながらも、前向きな改憲議論をも避けず丁寧な議論と合意形成を毎週重ね続けていくことこそ憲法審査会のあるべき姿だと考えますので、枝野会長を始め、船田、武正両筆頭の今後の御尽力をお願い申し上げ、私からの発言とさせていただきます。
2024-12-19
第216回国会(臨時会) 衆議院 憲法審査会 第1号 発言No.17全文を見る会長、ありがとうございます。
公明党の浜地雅一でございます。
我々公明党としましては、これまでこの憲法審査会を含めて我が公明党の憲法議論を引っ張ってこられました北側副代表が引退をされまして、今回、私どもはオブザーバーという立場ではございますが、私はオブザーバーとして幹事会に参加をさせていただきます。
甚だまだ力不足でございますけれども、しっかりと公明党の中でも議論を深め、これまでの伝統を承継しつつ、新しい憲法観も公明党でつくっていきたい、そのように決意をまず述べさせていただきたいと思っております。
私は議員になって約十二年でございまして、その半分以上、この憲法審査会に所属をさせていただきました。当時はなかなかこの審査会の開催がなかったわけでございますけれども、特に、森英介会長になられ、そしてまた、コロナ又はウクライナの有事ということで、やはり社会の事象が変わってきたという中において、毎週この憲法審査会が開催をされることを大変喜ばしく思っております。
そして、今回は少数与党と我々はなったわけでございますが、今回は会長が野党の枝野会長に替わられたわけでありますけれども、今日もしっかりと定例日に開催をいただいたことは、十二年前、私が国会に来たときに比べ、本当に前進をしているなというふうに実感をするところでございます。
公明党の憲法に関する考え方は、加憲、いわゆる加える憲法という考え方であります。では、一切今までの条文を動かさず何か加えなければならないのかというと、そうではなく、当然、現在の憲法の基本でございます国民主権、そして基本的人権の尊重、そして平和主義というものを変えない、これは普遍の原理である。その上で、様々な社会の事象に合わせながら、検討すべきものがあればしっかりと検討し、加えていこうというのが我々の憲法観であります。
ですので、コロナでなかなか国会機能が維持できなくなるのではないか、また、災害、そしてウクライナで起きました有事等で、国会の機能が果たせなくなるのではないかという社会の事象を我々は目の当たりにしました。
私は、やはり、憲法五十六条一項の「出席」の概念、これを我が衆議院の審査会で一定の決議をしたことも評価をしたいと思っております。ただ、これについては、参考人のオンライン出席にとどまっておりますので、本当の意味でのスタートは、本会議につきましてもオンライン出席ができるような体制を整えていくことを我々憲法審査会でも進めていかなければいけないと思っております。
その上で、選挙困難事態における国会機能維持、特に、国会議員の任期延長を含む議論を進めるべきであろうと思っております。
前回の衆議院選挙のときに、私は九州比例区なんですが、ある大分県のところで挨拶回りをしましたら、我が党の党員、支持者ではない方だったんですけれども、挨拶をしましたら、前衆議院議員の浜地雅一ですと名のりました。何で前衆議院議員なんですかと。衆議院は、解散中は実は身分を失っておりまして、私はただの人でございますと話しましたら、その方が、じゃ、もし、ここで地震が起きたり何か起きたときには、国会に戻られて、また議論されるんですよねというふうに、実は一般の方が言われたわけでございます。
ああ、なるほど、今の東日本大震災やウクライナの状況を見て、国民の皆様方の中にも、国会議員の解散中の権能であるとか、又は任期満了後の選挙中の権能については、やはり意識が高いんだなということを実感をいたしました。
ですので、そういった観点でいいますと、各会派からもお話がありますとおり、選挙困難事態における国会機能維持の条項につきましては、かなりの論点整理が進められておりまして、もう条文案に近いものが進められております。これを私は速やかに行うべきであろう、そのように改めて皆様方に申し上げたいというふうに思っております。
ただ、やはり、もう一つの論点としましては、中身も大事でございますが、国民投票法としての環境整備ということについても議論をすべきだと思っております。特に、令和三年国民投票法改正の検討事項についての議論を進めるべきであろう、そのように思っております。
特に、広報協議会の在り方であります。広報活動の全般についての賛否の平等が法定をされているのが国民投票広報協議会でありますので、まずは、ここの機能を充実させること、これがどういったものがあるのかということを議論をすべきだと思っています。
この中において、これは可能かどうか分かりませんが、この国民投票法、また、制定当時には想定をされていなかった、インターネットを用いた国民への情報提供や実施、そして、偽情報、誤情報を排除するための何らかの役割をこの広報協議会にも持たせられるかどうかについても議論をすることが大事であろう、そのように思っております。
今述べましたとおり、国会議員の任期延長を始めとする国会機能維持としての緊急事態への対応、そして、やはり、国民投票を行っていくためには、いま一度、広報協議会を含めた議論の集積がまず最優先の課題であろう、そのように公明党会派としては思っております。
最後に、その優先課題があった上で、別の論点を述べますと、公明党は以前、環境権というものを提案したことがございます。これにつきましては、よく、どうなっているんですかということを聞かれるんですけれども。
私は、去年、COP28に政府の一員として行かせていただきましたが、気候変動や温暖化に対する国際社会の動きというものは大変激しいものがあるというふうに感じました。ですので、いま一度、この環境権というものを、まずは国会議員の任期延長、そして国民投票法の検討を行った上でございますけれども、行うべきであろうと思っております。
ここで、一つ最後に申し上げたいのが、実はこの環境権につきましては、「国民は」で始まる主語、いわゆる国民の主観的権利やプログラム規定として捉えますと、実は、訴訟が乱発したというのがポルトガルで行った事例だというふうに聞いております。
我が党の現在の代表であります斉藤現代表が憲法調査会の幹事のときに海外視察をしたときに、この環境権、どのような書きぶりがいいかということになりましたけれども、ポルトガルでは、元々国の責務として書いていたものを国民の権利として書いた後に訴訟が乱発をしたということであります。
したがいまして、これも議論になったからでありますけれども、こういった環境権等につきましては、国民の主観的な権利ということではなく、「国は」で始まる、国に対する責務を課すような規定でなければならないというふうに思っております。
繰り返しますけれども、これもまずは国会機能維持というのが大きなテーマでございますので、それをしっかりと皆様方の同意を得ながら、仕上げてから、この問題も取り組んでいきたい、そのように思っております。
私からは以上でございます。ありがとうございます。












